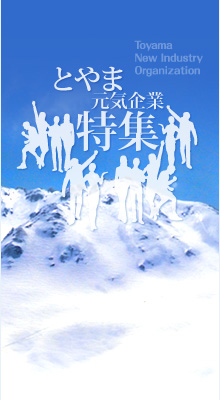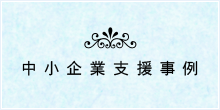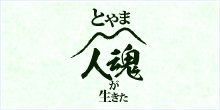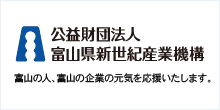TOP > 特集 > 廃材を利活用したアップサイクル創出プロジェクト
TONIO主催のイベント等の概要をご紹介。TONIOの視点は、ビジネスのトレンドをうかがい知る羅針盤。
廃材を利活用したアップサイクル創出プロジェクト
「BACCAIng」(ばっかいんぐ)始めました

カンファレンス会場に展示された、トヨックスの工場で
排出されるホース廃材やそれを樹脂と補強材などに
分離した例。
富山県と当機構では、令和6年3月に発表された「富山県ものづくり産業未来戦略」(改訂版)に基づき、サーキュラーエコノミー(循環経済)の構築など、新たな環境・社会価値の創出、産学官連携でのオープンイノベーションによる研究開発など、本県のものづくり産業の飛躍・発展に取り組んでいる。その一環として「廃材活用/アップサイクル」をテーマに、カンファレンスを開催。県内企業の産業廃棄物の状況を視察した後、廃棄物の利活用についてのディスカッションを行ってきた。このプロジェクトは、富山の方言「ばっかい」(=始末)にちなんで「BACCAIng」(ばっかいんぐ)と名づけられている。
1回目(R6.9.9)のカンファレンスは小矢部市の(株)ミヤモリ(テーマ:断裁くずの利活用)、2回目(R6.10.25)は富山市の(株)リッチェル(テーマ:プラスチック廃材の利活用)にて実施。先ごろ実施された3回目(R7.1.17)は黒部市の(株)トヨックスを訪問し、ホース廃材の利活用をテーマに議論が展開された。
本稿では3回目のカンファレンスの概要をお知らせしよう。
ホース廃材のリサイクルの現状は・・・

ホースやその継手を主に生産するトヨックスから出る
産業廃棄物やその利活用の現状についての質疑応答
を行う同社の得能真一氏。
まずは工場見学の後で実施された、同社の廃棄物の現状やエコ活動の概要についての紹介から。トヨックスの石原義寛氏の発表をまとめると以下のようになる。
同社の創業は1963(昭和38)年。ホースとその継手の製造販売をメインに行ってきた。直近では、EV車の導入やバイオマス原料を用いた製品の販売を行うなどを通じて、環境対応の取り組みを実施。2050(令和32)年のカーボンニュートラル実現を目指し、2030(令和12)年には2019(令和元)年の二酸化炭素排出量の50%削減を目標に環境対策に取り組んでいるという。
製造工程は、内管工程、補強工程、外被工程、印刷工程、巻取り工程に分けられる。工場内でのリサイクルは内管工程で出た、樹脂単一材料でできたチューブを粉砕して実施。補強・外被・印刷・巻取りの各工程の廃材は単一材料ではなく、リサイクル工場で補強材の糸と樹脂などに分離され、糸は廃棄処分されているそうだ。
粉砕した単一材料のホースは、同一のコンパウンド状のものを一定量混入し、再びホースとして製品化している。2023年の年間粉砕量は228t、リサイクル量は28.3t、リサイクル率は12.4%。社内でリサイクルできない複合材の粉砕量は、2023年では47tに達し、床材や農業で用いられる塩ビシートなどに用いられているという。
昨年8月からはシリコーン材料のリサイクルも開始された。月平均、4t前後のシリコーンを抽出し、新たなシリコーン商材として販売している。またシリコーン材のリサイクルについてはシリコーンチューブ、シリコーン垂れ流し、シリコーンホース(補強糸入)、シリコーンホース(補強糸モノフィラ入)は社外リサイクルを行い、シリコーンホース(補強糸鋼線入)、バラシ屑などは産廃処理に回しているという。
トヨックス全体では年間766.5tの廃棄物が排出され(2024年実績)、うち社内リサイクルは189.6t(24.7%)、社外リサイクルは244.5t(31.9%)、産廃処理は332.4t(43.4%)。産廃処理を少なくする方向で調整しているという。また同社の商品の中で、省エネや脱炭素に貢献できるものは、空気や液体の輸送効率向上やコンプレッサー関係、熱損失量の低減などがあり、サービス分野ではバイオプラスチックを使用した環境配慮型ホースやエア漏れ診断による省エネ性能の向上などがある。この診断は、工場の生産を止めることなく行うことが可能ということだ。
パーティーションや断熱に使えないか!

ホーズ廃材の利活用についての「気づき」や「アイデア」
を付箋に書き留め、それを掲示しながら利活用の議論
を進展させるAチームの様子(写真上)と全体会議での
発表の様子(写真下)。
トヨックスの工場から出る廃棄物を確認し、また同社の環境対応の取り組みについて説明を受けた後で、カンファレンス参加者はふた手(Aチーム、Bチーム)に分かれ、ホース廃材の利活用についての「気づき」や「アイデア」を付箋に書きとめた。それをチーム内で順次発表し、そこから議論を発展させて新たな「気づき」や「アイデア」を生み出し、全体会議の場で各チーム発表された。
Aチーム・深澤秀彦さん(本プロジェクトのクリエーター)の発表は以下の通り。
* * *
Aチームでは「1.仕組みのデザイン」、「2.つくる前から循環」、「3.消費者にどう伝えるか」、「4.製品そのままでアップサイクル」、「5.使われていないものの可能性」をテーマにして、お互いの気づきを発表しながら議論を深めました。「1.」と「2.」は近いところがありますのでまとめてお話しします。出てきた意見のひとつに、糸も樹脂製にできないかというものがありました。ホースと同一素材にすると循環のハードルが低くなるのではないかということです。
ただ、糸を樹脂にすると強度が課題になるかもしれません。そこで新しい素材が生み出され、新商品に結びつく可能性があるのでは、ということでした。
補強材を用いているホースは3層構造になっているということです。中の材質に糸を巻き、その上に樹脂を再度被せる。これについては、最初から補強材の糸を固定するのではなく、仮止めのような形でもホースとして機能するのではないか。そうすれば分別しやすくなるのではないかということです。
「3.消費者にどう伝えるか」では、リサイクルに臨む場に消費者に参加していただくのがいいのでは、という意見が出ました。一種のリサイクル体験の場です。廃材のホースを利用して何かをつくる場を設ける。そこでリサイクルのアイデアの蓄積ができるのではないかというのです。また正規品として市場に出せないB級品を、別ブランドとして販売してもいいのではないかという意見がありました。この別ブランドに関しては、1社単独では難しいので富山県全体で取り組むのもいいのではないかと思われます。
「4.製品そのままでアップサイクル」では面白いアイデアがたくさん出ました。ホースを巻いてクッションのように使えないか。それを防災用に活用できるのではないか、と。繋いでパーティーションのように利用する、あるいはそれを断熱ボードとして利用する。またそこに冷気や暖気を通して部屋の冷暖房に活用することもできるのではないか、というアイデアもありました。
そして最後の「5.使われていないものの可能性」では、用途転換や社会課題との結び付け方により可能性が広がるのではないか、というのです。分別された補強材の糸は、クッション性がありましたので梱包材に転用できる、という意見がありました。あるいは、ホースを枕に活用できないか、と。ユニークなアイデアとしては、工場では地下水をたくさん利用されているらしく、それが暖かければ(あるいは温めて)、足湯として活用できないか。その足湯の場へ、お湯を引くためにホースを活用する。従業員の満足度を高めるアップサイクルになるのではないかという意見です。
一般消費者向けに廃棄物の展示会を!

Bチームでの「気づき」や「アイデア」をもとにした
ホース廃材利活用の議論の様子(写真上)と全体
会議での報告の様子(写真下)。
続いてはBチームの発表。参加者の気づきなどをまとめて報告したのは板野一郎さん(本プロジェクトのクリエーター)だ。
* * *
私たちは工場の視察の中で気づいたことをざっくばらんに書き出し、話し合いました。順不同ですがそこで出た気づき、アイデアを紹介します。アパレル関係の方から、「私たちの業界ではB級品は値段を下げて販売し、C級品は廃棄しますが、今日のテーマのホースでは、C級品に相当するものをリサイクルやアップサイクルして販売しようという姿勢に感動しました」とありました。ただ複合材料の仕分けには難しい点があることを実感されたようです。複合材料に関しては、補強材を単一化できないのか、あるいは鋼線に替わるリサイクルしやすい材料はないのかという意見がありました。
これから申し上げることはサーキュラーエコノミー(循環経済)全体の課題と言ってもいいと思いますが、一般の消費者向けに廃棄物の展示会を行うことは意義のあることだ、という発言もありました。
不良品のホースのリサイクルについては、粉砕せずにホースの形を利用することも考えてもいいのでは、と。例えば楽器に応用することはできないかというのです。同様の意見として、不良品のホースを子どもに渡し、それを使った遊び方の開発をするのもよいのではないか、と。また利活用の方法の開発については、一般消費者の感覚に近い新入社員に、自由に意見を述べることができる場を設け、そこから利活用のヒントを拾い上げてはいかがかという意見もありました。
また先ほどのAチームの発表にもありましたが、一定の長さに揃えたホースに空気を充填して両端をふさぎ、それを連結してクッションとして使うアイデアもありました。
そもそも論としてこんな意見もありました。トヨックスさんでは200を超えるアイテムのホースを製造されている。ユーザーのニーズに応えて品数を豊富にされたことは理解できるが、アイテム数や素材を集約することにより廃棄物の量は減るのではないですか、というものです。同様に、ユーザーのニーズに応えてホースの機能をさらに上げることを志向されていますが、機能を上げれば上げるほど、素材の分離が難しくなるなどの面があるのではないか。もしそうなら、リサイクルする際の素材の分離・分別を考えながら、商品開発を進めたらよい、という声もありました。
* * *
富山県と当機構では、令和7年度もサーキュラーエコノミー(循環経済)を推進するため、異業種連携による新たな価値創出に向けたカンファレンスを開催し、情報発信を行う予定だ。「BACCAIng」のホームページやInstagramをご覧になり、あるいはこのレポートに接して、読者の皆様の工場の廃棄物の利活用・アップサイクルに関心・興味を持たれた際は、事務局までご一報を。貴社でのカンファレンス開催を検討します。
- 「BACCAIng」について URL1:https://baccaing.jp
- 「BACCAIng」について URL2:https://www.tonio.or.jp/search/circular-economy/
- 「BACCAIng」についてInstagram:https://www.instagram.com/baccaing_toyama/
○問合せ先
所 在 地 :〒930-0866 富山市高田529 技術交流ビル
(公財)富山県新世紀産業機構 イノベーション推進センター 連携促進課
TEL 076-444-5606 FAX 076-433-4207
URL : https://www.tonio.or.jp
作成日 2025/03/21
- サーキュラーエコノミーとは何か?
- T-Messe2025富山県ものづくり総合見本市開催
- アルミのグリーン化でも主導的役割を!
- 廃材を利活用したアップサイクル創出プロジェクト
- デジタルツール初心者向け講座
- 「ものづくり未来戦略」の改訂産学官連携をより推進して…
- ヘルスケア産業も富山の成長産業に
- T-Messe2023富山県ものづくり総合見本市開催
- よろず支援拠点開設10周年
- 広域商談会・取引あっせん
- 富山県よろず支援拠点
- [ 特集 ]中小企業活性化協議会
- 「T-Messe2021」をオンラインで開催コロナ禍が生んだ新しいビジネスショーのスタイル
- TONIO創立20周年記念特集
- 事業承継&佐野政製作所
- コロナ対策「再起支援」で1,000者余りを支援。本年度は「リバイバル」でさらなる後押しを!
- オンラインセミナーでも企業活動を支援海外展開に方向性を見出す企業も
- はじめての起業・創業セミナー
- 令和元年度 とやま起業未来塾(シェアライフ富山 社長 姫野泰尚氏 インタビュー)
- 「とやまヘルスケアコンソーシアム」設立
- 富山県ものづくり総合見本市2019開催
- とやま次世代自動車 新技術・新工法展示商談会in TOYOTA
- とやま次世代自動車 新技術・新工法展示商談会in MAZDA
- 富山県事業引継ぎ支援センター活用事例
- 「アジア経済交流センター」へと名称変更
- 夢・情熱・志が集う「とやま起業未来塾」
- 富山県ものづくり総合見本市2017開催
- とやま次世代自動車技術・新工法展示商談会開催レポート
- とやま産学官金交流会2016
- 若い研究者を育てる会30周年記念講演会
- 富山県よろず支援拠点
- とやま産学官金交流会2015
- 「富山県よろず支援拠点」経営戦略セミナー
- 富山県ものづくり総合見本市は商談数が急増