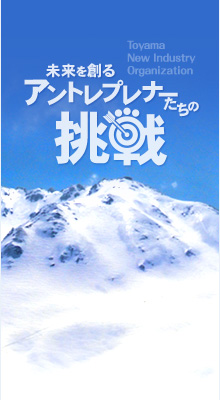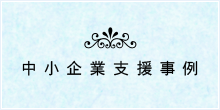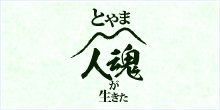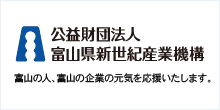TOP > 未来を創るアントレプレナーたちの挑戦 > 第82回 ハミングバード(Humming Bird)
TONIOに集う夢・情熱・志。気鋭のアントレプレナーたちとTONIOが紡ぐ挑戦の棋譜を読む!
第82回 ハミングバード(Humming Bird)
チョコレート専門店を富山で創業
地元の農家や小学生・高校生とも交流し・・・

静岡から富山に移住してチョコレート専門店「ハミン
グバード」を創業した時女宗久さん(写真上)と、総
曲輪通り商店街の「ハミングバード」の正面(写真
下)。
「最初はチョコレートの甘さが、しばらくしてイカの塩味が口の中に広がります。コーヒーや日本酒とともに召し上がっていただくことをイメージして商品化しました。当店のラインナップの中では、このホタルイカ入りチョコレートは大人気。物珍しさからか自家用の他に友人などへの手土産としてお買い求めになられる方も多いようです。どうです、ひとつ試しに……」
時女宗久(ときめ・むねひさ)さんに勧められて封を開けると、今まで嗅いだことのない高級そうなチョコレートの香りが鼻腔を刺激する。ホタルイカは乾燥してパウダー化されているためか生臭さはまったくなく、イカの塩味がチョコレートの甘さを一層引き立たせている。
ここは富山市総曲輪通り商店街にあるチョコレート専門店の「ハミングバード」。カカオ豆からチョコレートができるまでの全工程を、ひとりで手づくりしているお店だ。時女さんはそのオーナーで、3年前の秋、静岡から富山に移住してお店を開いた。
ハミングバードでは、ホタルイカの他にシロエビ、庄川ゆず、灘浦みかん、氷見うどん、こんぶ、ブルーベリーなど富山にゆかりのある食材を、ガーナやコロンビア、カメルーンなどから仕入れたカカオ豆を原料にしたチョコレートに練り込んで、富山の活性化を目指している。ちなみに店名の「ハミングバード」はアンデスの民話をまとめた『ハチドリのひとしずく いま私にできること』(森林火災に際し、一滴の水を運んで消火しようと励むハチドリに対して、森の動物たちは笑う。ハチドリは「私は、私にできることをしているだけ」と答えて……というあらすじ)に由来し、「自分のできることをやろう」という時女さんの思いを表したものだ。
今回の「アントレプレナーたちの挑戦」では、チョコレート専門店ハミングバードを創業した同氏の足跡を追った。
チョコレート専門店を富山で!

ハミングバード店内の様子。一方の壁際では、商品を
紹介し(写真上)、その対面にイートインのコーナー
を設け、コーヒーなどとともに楽しむことができる
(写真下。)壁の上部では、パネルでチョコレートづ
くりの工程を説明している。
学卒後、高速道路のサービスエリア(SA)を運営する会社での勤務経験を有する時女さん。飲食や土産物コーナーを主に担当していた。経験を積むに従って職階が上がり、差配の範囲は広くなったものの、今一、充実感を持てなかったという。そうしたある休日の昼下がり、大手コーヒーショップでくつろいでいると、そこで働く従業員の様子に目が釘づけになったそうだ。
「スタッフの皆さんは楽しそうに働き、生きがいを感じているようでした。それに対して私がいた職場にはそういう雰囲気はまったくなく、生き生きと働く店員さんを見て『こういう職場で働きたい』と思ったのです」
時女さんはそういって二十数年前の転職のきっかけを思い起こした。念願叶ってそのコーヒーショップで働き始めると、社会人としての自覚や、企業が担う社会的責任などを意識するようになり、「社会人としての基礎を形成することができた」そうだ。
十数年後、縁あって前のSA運営会社に戻ったものの、数年後、コロナ禍によって交通量が激減。かつてのような忙しさはなく、時間に余裕ができたことを機に、時女さんはある大学のMBA(経営学修士)の基礎クラスを受講し、起業も含めて自身の将来の可能性を探ったのだった。
「この時、コーヒーショップでの創業も頭をよぎりましたが、競合が多い世界ですからコーヒー1本では厳しいだろうと思いました。そこでコーヒーと相性がよく、また地元の食材と組み合わせることができるもの……と突き詰めていった結果、チョコレートに辿り着いたのです」(時女さん)
創業にあたり3つのことを検証

同店のチョコレートの一例(写真上)。左から
「Clombia-Arhuacos」(コロンビア産のカカオ豆使
用。同店一番人気)、ホタルイカ入りチョコレート
(ガーナ産カカオ豆使用)、庄川ゆず入りチョコレー
ト(ガーナ産カカオ豆使用)。またホットチョコレー
トや各種コーヒーの他に、クラフトコーラなどのドリ
ンクも飲むことができる(写真下)。
そこでチョコレート専門店への転身を決意した時女さん。SA運営会社を退職し、静岡のチョコレート屋さんで修業することに。“BEAN to BAR”(カカオ豆からチョコレートができるまでの全工程を、自社で一貫管理して製造するスタイル)を確立するために技術を磨き、一方では創業の候補地探しに勤しんだのだ。
「実は父方の祖父母は富山にいて、子どもの頃、夏休み・冬休みにはよく遊びに行き、ブリや昆布締めなどの富山のおいしい食材を食べた記憶が残っていました。祖父母の晩年には、父は介護のために静岡と富山を車で往復し、また後には富山に引っ越して面倒を見ていました。いずれ私にもそういう時がくることは容易に想像できます。ならばいっそのこと富山で起業して、生活の基盤も富山で築いた方がいいのではと思った次第です」
こう語る時女さんは、生まれは千葉県、大学時代は東京で過ごし、サラリーマン時代の大半は神奈川県、静岡県で過ごした。普通なら土地勘のあるところでの起業、潜在消費者の多い地での出店を考えるだろうが、時女さんは迷わず富山市を創業の地に選んだのだった。
「私はハミングバード創業にあたり、“自分のやりたいことか”“世の中から求められていることか”“プロの目から見てどうか”を徹底して検証しました。総曲輪通り商店街への出店や地元の食材を使うことは、地域活性化に繋がりますからウェルカムでしょう。また総務省の『家計調査』によると、富山市は1人あたりのチョコレート消費量は多く、よくベスト10に入り、時にはトップ3にランクインするほどですから、事業の可能性があるのではないかと判断しました」(時女さん)
創業支援のメニューが豊富なことも魅力的だったという。時女さんが活用した富山市の「みんな起業家、集まらんまいけ!」は、ビジネスプランのアイデアを競うコンテスト。担当者が伴走し、事業計画の作成を手伝ってくれたそうで、その過程でプランのブラッシュアップをすることができたようだ。
また当機構の「富山県よろず支援拠点」では、ITを活用しての事業の効率化や広報などの指導を受けた他、「とやまUIJターン起業支援事業」(令和4年度)の採択を受けて、助成金をカカオ豆を焙煎するための機械の導入にあてるなど創業の準備を進めたのであった。
夏休みの自由研究に協力し、万博にも・・・

富山商業高校の生徒に、模擬店出店にあたってのお店
の運営についてレクチャーする様子(写真上)と、
「EXPO2025大阪・関西万博」のカメルーンブース
で、同国産のカカオ豆を使用したハミングバードの
チョコレートの試食品を配布する時女さん(写真下)。
お店がオープンしたのは令和5年1月のこと。富山でのチョコレート専門店の開業は珍しく、地元のテレビをはじめとした各種メディアがこぞって取材することになった。「おかげでオープン早々注目されて、ロケットスタートを切ることができた」(時女さん)ようだ。その結果、集客や販売は比較的順調に伸ばすことができたという。
「難しかったのは、地元の食材を仕入れるためのルートの確保でした。例えば庄川ゆずを買い付けようと、開業前の秋に庄川地区に足を運びました。ところがその年はゆずが不作で、安定的に仕入れるためのルートの確保ができませんでした。そこで当店の向かいでお店を構える『地場もん屋』さんに相談すると、ゆずを出荷している農家を紹介していただいたのです」
かくいう時女さんは、地元の食材を新鮮で、おいしい状態で仕入れることを旨とし、生産者に近いところからの調達を心がけているという。
地元への協力は、チョコレートの一貫生産ができる設備を有することから、小学生の夏休みの自由研究向けに「カカオ豆からチョコレートをつくろう」と呼びかけて、ワークショップを開催。富山商業高校からの依頼では、高校生の模擬店(チョコレート店)出店にあたっての仕入れ、店舗のレイアウト、販売、売上計算までの全てを高校生自身に考え、実行させ、時女さんがそれをサポートすることも行ってきた。
また先ごろ閉幕した「EXPO2025大阪・関西万博」では、カカオ豆の仕入れ先からの要請を受けて、カメルーンブースでチョコレートの試食品を配布するとともに、国連パビリオンではハミングバードのチョコレートの特徴などを紹介する機会も得たのだった。
独立前、コーヒーショップで働いた時にCSR(Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任)に関心を持ち、「総曲輪通り商店街への出店と地元食材を用いることにより地域の活性化の一助になりたい」と夢を抱いた時女さんにとって、こうした連携は予期していなかったこととも思われるが、「ハミングバードが富山のお役に立てるのはうれしい」の一言には、実感がこもっていた。
- 「富山県よろず支援拠点」について
- 「とやまUIJターン起業支援事業」について
(この事業は「起業なら富山!創業・移住支援事業」に引き継がれています)
連 絡 先 :ハミングバード(Humming Bird)
所 在 地 :〒930-0083 富山市総曲輪3-6-15 サザンクロスビル1F
従業員数:0名
T E L :090-8778-9880
U R L :https://www.hum-toyama.net
作成日 2026/01/06
- 第82回 ハミングバード(Humming Bird)
- 第81回 楽ya(たのしや)
- 第80回 菓子屋Chemin(シュマン)
- 第79回 合同会社ポラリス
- 第78回 株式会社オカッテン
- 第77回 源流居酒屋
- 第76回 bel tempo(ベルテンポ)
- 第74回 株式会社UNISPOT(ユニスポット)
- 第73回 もてなし蔵 和on
- 第72回 縁、ル・リアン
- 第71回 けんとれ接骨院
- 第70回 FRUCRU(フルクル)
- 第69回 tototo(トトト)
- 第68回 株式会社とやまなび
- 第67回 株式会社ユメミガチ
- 第66回 株式会社ディライト
- 第65回 株式会社DQ Solution
- 第64回 トモスメイカー合同会社
- 第63回 TENKIN NOTE (転勤ノオト)
- 第62回 株式会社IMATO
- 第61回 株式会社SUDACHI
- 第60回 Latticework BREWING COMPANY
- 第59回 カフカルチェ
- 第58回 とみやカフェ(株式会社TOCO[トーコ])
- 第57回 株式会社ワプラス
- 第56回 mamasky(ママスキー)
- 第55回 ますのすし本舗ちとせ(株式会社千歳)
- 第54回 食パン専門店 ファイブ
- 第53回 本格手打ち蕎麦「福籠」
- 第52回 お宿 いけがみ
- 第51回 Ogino Guitars(オギノ ギターズ)
- 第50回 株式会社キレイサービス
- 第49回 株式会社岡本(呉服の岡本)
- 第48回 つけめん えびすこ((株)A-STYLE)
- 第47回 株式会社ミガキ