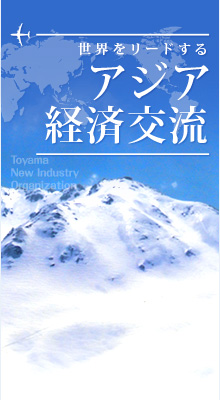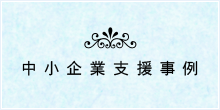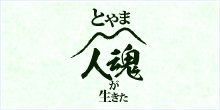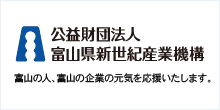第56回 株式会社スギタニ 海外販路開拓商談会 とやま食材レストランコラボフェアinバリ オーストラリア県産品プロモーション事業 米国向け食品輸出商談会・富山フェア 台湾経済ミッション(商談会・現地視察) TONIO Web情報マガジン 富山
TOP > 世界をリードするアジア経済交流 > 第56回 株式会社スギタニ
TONIOの支援を活用しながらアジアを中心とした世界へ羽ばたく富山の中小企業をご紹介。
第56回 株式会社スギタニ
日本の伝統食品「麩」を世界へ!
チャレンジ初年度から成果が・・・

(株)スギタニで、日本の伝統食品の麩の海外
展開を試みてきた杉本英子副社長(右)と杉谷
美咲緒専務取締役(左)。
「実は私、以前、中国に留学していたことがあります。世界各国から多数の留学生がいて、豆腐や納豆などの日本の伝統食品は海外の人にも徐々に知られていました。しかし麩はほとんど知られておらず、悔しい思いをしました。麩のルーツは中国の麺筋(めんきん)にあるといわれていますが、私が当時見た麺筋は日本の湯葉を分厚くしたようなもので、麩とは似ても似つかぬものでした。中国の人々も麩についてはほとんど知らなかったようです」
そう語るのは、麩の製造販売を主な業務とする(株)スギタニの専務取締役の杉谷美咲緒さん。昨年から麩の海外販売を模索し始め、すでにいくつか販路を開拓しつつある小矢部市の食品メーカーの切込隊長である。
同社の創業は昭和2(1927)年。もうすぐ100周年を迎える歴史のある企業だ。主な取扱商品は焼麩・生麩で、冷凍野菜や花びらのように切り込んだ野菜の輸入販売の他に、おせち料理の企画・製造も手がけている。フットワーク軽く、全国の食品問屋や小売店を精力的に訪問し現場の声を吸い上げており、取引先の問屋に誘われて食品関連の展示会に商品を並べたことはあったものの、後に紹介するような商談会、展示会、販促プロモーションなどに単独で参加して商談を行うようになるなど、しかもいきなり海外のバイヤーと取引条件の交渉を行うようになるなど、令和6年の初めには想像すらできなかったようだ。
そこに至る経緯を紹介しよう。
国内の展示会に参加したこともないのに・・・

同社の主力商品の調理例。写真上は、角麩の煮
物。彩りをよくするために吹き寄せ麩を載せて
いる。写真下は、生麩の天ぷら。結び麩、てま
り麩、あやめ麩などの6種の生麩を使用し色鮮
やかにしている。
スギタニと当機構のご縁は、平成30年頃に始まった。全国に販路を持っているとはいえ、食の欧米化により麩の消費に陰りが見え始め、同社では危機感を抱きつつあったという。杉谷専務が振り返る。
「少子化、人口減少が目の前に迫り始め、このまま手をこまねいていてはダメだと思いました。そこでホームページを用いての販路開拓にはすでに取り組んでいたのですが、より効果的なホームページのつくり方や、ホームページを活用しての消費者ニーズのつかみ方のセミナーを新世紀産業機構が行っていたので、そのノウハウを学ぼうと受講したのがご縁の始まりでした」
ところが翌年の暮れには新型コロナウイルスが猛威をふるい始め、国内でも、翌令和2年には緊急事態宣言が発出されるなど、混乱の渦に飲み込まれたのだった。
杉谷専務が続ける。
「令和5年に入ってコロナの流行は収まりつつありましたが、少子化や人口減少云々の前に、飲食店に元気がなく、一般のお客様の消費意欲もすぐには回復しないのではないかという危機感を覚えました。そこで麩の海外展開を思いついたのです。学生の時は、海外の人々に知られていないことを悔しく思いましたが、今回は『伸び代がある』と前向きに捉えることができました」
令和6年度に入ってしばらくして、杉谷専務は当機構に海外展開についての相談を持ちかけたところ、「オーストラリア県産品プロモーション事業」(令和7年2月実施)を紹介され、その場で参加を決意。また後には「海外販路開拓商談会」(令和7年1月実施)や「とやま食材レストランコラボinバリ」(同前)が計画されていることを知ると、こちらも合わせて申し込んだのだ。
「自社単独で、国内の展示会・商談会にも参加したことのなかった当社が、いきなり海外のバイヤーとの商談に臨むなんて、冒険以外の何物でもありませんでした。何を準備していいかもわからず、先に海外展開を始めた食品メーカーを訪ねて、いろいろレクチャーを受けたものです」
杉本英子副社長はこういって「失敗から学んだことが大きな成果になったこともあります」と続けた。
「豚肉の代用品として…」

「とやま食材レストランコラボフェアinバ
リ」で現地のレストランの協力を得て、富山県
産品を使った料理を紹介するメニュー表(写真
上)。スギタニの麩は三品に用いられたが、「生
麩と野菜の揚げ出し」(写真下)のオーダーが
最も多かった。
そのひとつが「賞味期限」の問題だ。初めての海外バイヤーとの商談となった「海外販路開拓商談会」では、オーストラリアに流通網を持つバイヤーが同社の焼麩に興味を持ったものの、賞味期限がネックになったという。
「日本国内では1年の賞味期限で十分なのですが、海外に輸出するとなると現地の小売店に並ぶまでには日数がかかります。輸送コストを抑えるために、コンテナ1本分がいっぱいになるまで国内で一時保管し、そこで数カ月かかることも…。そうすると、現地の小売店に並ぶ頃には“半年も余裕がない”ということになりかねません。そうしたことを加味すると、賞味期限は1年半とか2年あった方がいいことがわかりました」(杉谷専務)
“初めての商談”は成約には至らなかったものの、賞味期限について認識を新たにする機会になったようだ。
続いては「令和6年度とやま食材レストランコラボフェアinバリ」(令和7年1月実施)への参加だ。このフェアでは、現地のレストランの協力を得て、参加企業の食材を用いたメニューを1カ月提供し、お客様の反応を踏まえた上で現地のバイヤーと商談しようというもの。スギタニではレストランのスタッフが考案した沖縄料理風の「キムチの麩いりちー」、「生麩の田楽」、「生麩と野菜の揚げ出し」の三品を提供したところ、現地バイヤーが車麩に興味を示し、のちの商談の結果、取り扱いが検討されているという。
「バイヤーのお話を総合すると、和食レストランの関係者は『豆腐とか納豆の他に、日本の伝統食品には麩もあった。今まで麩を忘れていた』と評される方がいらっしゃったようです。また現地レストランの方々は、『イスラム教徒には、豚肉の代用品として油と相性のよい麩を用いてのレシピ展開が可能ではないか』と話していらっしゃったようです」(杉本副社長)
例えばトンカツの衣の中を、車麩に変えようというのか…?
「将来的には中東やアフリカにも」

オーストラリアの食品スーパーで行われた「と
やま県産品プローモーション事業」の様子(写
真上・下)。同社では来店客に試食も勧め、副
社長、専務の2人が接客を務めた。
「令和6年度オーストラリア県産品プロモーション事業」(令和7年2月実施)も、海外展開初年度の同社にとっては大きなつめ跡を残したようだ。このプロモーション事業は、オーストラリアの日本の食材を販売する食品スーパーで、商品のテスト販売を行うもの。スギタニでは小細工麩の反応を確かめようとその準備を進めていたところ、スーパーのオーナーから「試食販売をしてお客さんの反応を確認してみては…」と提案され、急遽(きゅうきょ)、試食販売を行うことに。日本風のお吸い物に小細工麩を浮かべて来店客に試食していただいたところ、日系の方々からは「懐かしい」という声が多数聞かれ、現地のお客様からは、「何これ? きれい!」と絶賛されたという。
そして展示即売会終了後の商談では、小細工麩の取り扱いが決定。6月初旬に行ったこの取材までに、追加のオーダーもあったそうだ。
令和6年度、インドネシアとオーストラリアへの麩の販路開拓に成功した同社。海外への輸出を試みた初年度に、2件の商談を成立させたわけだが、社員の意識が変わりつつあるという。
杉本副社長が語る。
「それぞれの商談の様子は、社員にも報告しています。商品が評価された点はもちろんですが、ネックになって商談が進まなかった点も話しています。最初のうちは、『麩を輸出しようとしているみたいだ』と遠巻きに見ていた社員も、バイヤーの評価を聞くたびに関心を持ち始めました。最近では、『○○について、輸出のネックにならないように商品開発や製造法の改善を進めてみましょうか』と提案してくれるようになったのです」
令和7年度に入って同社では、海外バイヤーを対象とした「“日本の食品”輸出EXPO2025」(東京ビッグサイト、7月開催予定)への出展を決めた。自社単独では初の展示会出展で、ブースのデザインやパネル・ポップの制作、販促ツールの作成(英語版、中国語版)などに追われる他、当機構が本年度に計画している「米国向け食品輸出商談会・富山フェア」(オレゴン州、11月開催予定)や「台湾経済ミッション(商談会・現地視察)」(台北市、8月開催予定)にもエントリーし、商談の機会を1つでも増やそうと意気軒昂だ。
最後に、輸出関連を総括する杉谷専務が、同社の今後の抱負をまとめた。
「この1年、いろんな国のバイヤーとお話しする中で、どの国の方々も興味を示してくださいましたので、中東やアフリカの国々への展開についても可能性があると思っています。そしていずれは豆腐や納豆と同じように、日本の伝統食品として世界の人々に愛されるようになる…。そうなると確信しています」
- 海外販路開拓商談会について
- とやま食材レストランコラボフェアinバリについて(令和6年度終了分)
- オーストラリア県産品プロモーション事業(令和7年度事業)について
- 米国向け食品輸出商談会・富山フェアについて
- 台湾経済ミッション(商談会・現地視察)について
連絡先/株式会社スギタニ
〒932-0032 小矢部市地崎173
TEL 0766-67-0419
FAX 0766-68-1086
URL https://www.sugitani1.co.jp
作成日 2025/07/03
- 第56回 株式会社 スギタニ
- 第55回 有限会社 中村海産
- 第54回 前田薬品工業株式会社
- 第53回 株式会社丸米製菓
- 第52回 株式会社ハリタ冷蔵
- 第51回 株式会社山口久乗
- 第50回 有限会社片口屋
- 第49回 日の出屋製菓産業株式会社
- 第48回 海外販路開拓商談会開催
- 第47回 有限会社京吉
- 第46回 中国向けライブコマース「富山県工芸品首播」実施
- 第45回 有限会社グリーンパワーなのはな
- 第44回 株式会社海津屋
- 第43回 株式会社柴田漆器店
- 第42回 株式会社やぶうち商会
- 第41回 かね七株式会社
- 第40回 海外バイヤー招へい商談会を開催
- 第39回 タイ経済ミッション派遣
- 第38回 株式会社ナガエ
- 第37回 ファインネクス株式会社
- 第36回 中国(上海・重慶)経済視察ミッション開催
- 第35回 海外バイヤー招へい商談会開催
- 第34回 株式会社ハナガタ
- 第33回 山元醸造株式会社
- 第32回 株式会社加積製作所
- 第31回 氷見稲積梅株式会社