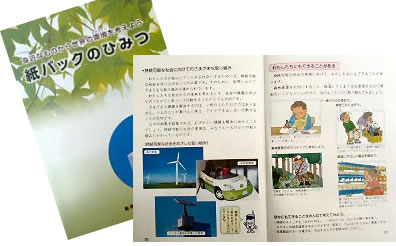|
|||||||||||||||||
| トナミ運輸株式会社 グリーンエネルギー研究所 |
3年前にはミニカーを走らせ、また昨年は軽トラを走らせ、双方の記者会見は編集子も見せてもらった。今回の取材は同社のこの取り組みがテーマであるが、それにしても何故、運送会社がここまで熱心に、廃アルミの再利用に取り組むのか。まずは事の経緯からうかがった。 |
| 実験開始は後発であったが… |
トナミ運輸の水木伸明さんに相談があったのは平成18年のこと。水木さんは同社では経営企画本部に席を置き、また運輸・鉄道・航空部門で最初に環境カウンセラー(環境省登録)の資格をとり、ビジネスチャンスを求めて全国を飛び回っていた時に、あるパルプ会社の上層部と出会って、先の相談を持ちかけられたのだ。 さっそくサンプルを送ってもらった。段ボールから出てきたのは右の写真で紹介するような、アルミ箔の切れ端といっていい代物だ。 「正直いって、これを前にどうしたものかと悩みました。他でもリサイクルについて研究しているようでしたが、いい結果は出ていない様子。一緒に環境問題に取り組んでいる友人に相談してみると、中国の大学に協力してもらって、分離できるかどうか実験してみよう、というのです」 水木さんは、この“ゴミの山”に思いを馳せた。当時国内では、すでに6つの大学がアルミ付き紙パックのリサイクルに取り組んでいたが、成果は出ていなかった。それだけに不安は大きく、「今さら…」という気持ちが起こる半面、「先行している大学とは違う方法でやってみよう」と環境問題に取り組んでいる友人と話がまとまり、中国の大学に実験を依頼。そのうち国内の大学は相次いで実験から撤退してしまったが、後発の同社は諦めることなく取り組んだのであった。 国内では、どの大学も取り組まなくなって2週間ほどした時のことだ。「こんなものがとれました」と中国の大学が分離したものを送ってきた。ビンには、処理前よりは大きなアルミ箔のようなものと、オイル状の液体が。とりあえず分離には成功したようだ。 平成20年より、このプロジェクトに取り組むようになった村椿浩司さんが解説する。
|
| 公的支援で技術の確立 |
そんな時だった。富山高等専門学校(当時は富山工業専門学校、21年10月より現校名、以下同)の丁子(ちょうじ)哲治教授と出会って相談すると、「燃料電池に利用できるではないか」と即答。「アルミと水酸化ナトリウムを化学反応させて水素を発生させ、それを燃料電池に利用する。副産物のアルミン酸ナトリウムは別途工業的に利用できるため、廃棄物はまったく出ない」というのだ。 さっそく実験してみると、当初こそ燃料電池に適する濃度の水素ではなかったものの、改良を加えていくうちに利用可能な水素となり、後にミニカーを走らせるまでになったのである。国内の名だたる大学が実験を中止した後だっただけに、この取り組みは、にわかに注目され始めた。 一連の取り組みの中で、アルミを回収するシステムとその燃料電池への利用について特許を出願(平成19年2月)。また当機構の「新商品・新事業創出公募事業」(平成19年度)の助成を受けて、トナミ運輸、富山高専、富山県工業技術センター、そして最初に相談を持ちかけたパルプ会社などが共同して、その技術の確立に乗り出した。 |
| モデル地区で発電を… |
このカートリッジ式水素発生装置についても、特許を出願(19年10月)。これらが報道されると問い合わせが多数入るようになった。特に、全国の自治体の反応はすごい。アルミ付き紙パックの他に、内側にアルミが用いられたスナック菓子の袋、薬や化粧品のアルミ付きパッケージなどの廃棄物は、焼却してもスラグ状態で残るため、従来は埋め立てしか処理方法がなかったのであるが、分離して、燃料電池に利用することができると情報が伝わると、自治体は蜂の巣を突ついたような反応を見せた。ある自治体からは、200世帯ほどのモデル地域で、このシステムを使って電気の供給をしてみないかと打診があったほどだ。 |
| 国の委託事業に採択 |
今までの共同開発者(富山高専、県工業技術センター、パルプメーカー)以外にも協力を求めなければならないが、何よりも開発の資金が必要となってくる。そこで水木さんは、環境省の「地球温暖化対策技術開発事業」(平成21年度)と、同じく環境省の「地域における容器包装廃棄物3R推進モデル事業」(同前)に応募したのであった。 前者は、低炭素社会を目指す基盤技術の実用化を促進するための技術開発・実証を進める事業だ。全国からの応募数は70件あり、同社のプランを含めた9件が採択。研究開発の委託費(年4,680万円)が平成21年度から3年間交付されることとなった。 これを受けて、開発に拍車がかかったのは言うまでもない。富山大学大学院、不二越(富山市)などとともに、カートリッジの開発を急ピッチで進めることになった。 また後者の事業は、容器包装廃棄物の3R(排出抑制:Reduce、再使用:Reuse、再生使用:Recycle)の先進的な取り組みについて、その普及や効果の検証など進めるもので、これも採択されて事業委託費 (195万円)が交付された。そして富山市、金沢市などで、アルミ付き紙パックの回収が試みられるようになったのである。 冒頭に紹介した、アルミ付き紙パックをアルミとパルプに分離して、パルプを再利用するケースはまだ少ない。アルミ付き容器の大半は、埋め立てか可燃物に混ざった状態で焼却されているのが実態だ(焼却されてもスラグとして残り、埋め立て地に運ばれる)。飲料用のアルミ付き紙パックの場合、5%程度のアルミがあることによって、95%の紙の再利用が阻まれている、といってもいいわけだ。 その意味では、このプロジェクトの推進のためには、技術開発とともにアルミ付き容器廃棄物の分別回収という、社会の仕組みもつくっていかなければならず、3R推進モデル事業に採択されたことは意義あることであった。 |
| あと数年で“エネルギーの山”に… |
廃車同然の軽トラを改造し、ハイフォークリフトのモーター、バッテリーを転用し、また水素発生装置も原理的で簡便なものを使ったため、試走に要した費用は20万円もかかっていない。単純に比較はできないが、自動車メーカー等で、試験的に開発されている水素ボンベ搭載・燃料電池車の費用(1台当たり2億円前後)を思うと、カートリッジ式水素発生装置による燃料電池車の方が、安価に実用化できるのではないか…と編集子は技術に素人ながら思った。 「今は車を走らせることが注目されていますが、このシステムのポイントは、安全に、どこでも発電できることです。土木や建設などの工事現場では、場所によっては電線を通すための工事が先行して行われますが、このシステムを使うとそれが不要になる場合もある。ですから、カートリッジ式は極めて可能性を含んでいるのです」 水木さんはこの言葉で取材を締めくくり、「僕は技術の専門家ではなかったから、ある意味、怖いもの知らずに取り組め、皆さんの協力によってここまで来れた」と付け加えた。“ゴミの山”は“エネルギーの山”に変わりつつある。金の卵はもう数年で生まれそうだ。
|
| 作成日2010.02.10 |
| Copyright 2005-2013 Toyama New Industry Organization All Rights Reserved. |